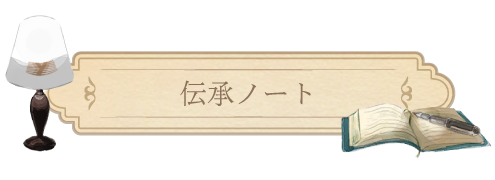
私は60年にわたり電気工事の管理に携わってきましたが、大変なことになってしまった一つの現場での体験を忘れることができません。
それは阪神淡路大震災の翌年(1995年)にあった、某国立大学での基幹整備工事での出来事です。大震災に遭っても、3日連続で運転できる発電機を各部毎に設置するという工事でした。この現場の事務所に空き巣が入ったのです。
工程の中頃でした。パソコン、カメラ、電卓、その他諸々のものが盗難に遭い、途中経過を証明する資料がなくなり、最終検査に大変苦労することになってしまったのです。特に、写真がないと見えない場所、埋設配管、隠蔽部分の施工状況等、図面通りに施工できているかどうかが分からないためです。
この経験から、写真記録の大切さがよくわかりました。また、現場事務所での身の回りの物品の管理をしっかりとしないと、大変な事態になってしまう事を身をもって学びました。
一方で60年の間には大切なことも教わってきました。それは『4つの真心を尽くすこと』です。真心を尽くす事、これはお金のかからない、ただでできる心の仕事だという事です。そしてこの4つの真心を尽くすことができないようでは信用は生まれないという事です。
4つの真心とは何でしょう?
あなたは①【挨拶】ができていますか?②【笑顔】ができていますか?③【気配り】(適度な)ができていますか?、そして④【親切】ができていますか?あなたも是非、自分自身に問うてみてください。(竹内寿一)
私は21話にも書きましたが、60年余にわたり電気工事の管理に携わってきました。今の工事現場では、全てという位、コードレス機器を使用して作業をスピーディーにこなし、作業時間を短縮し、工数の削減を図っています。では、昔はというとどのように作業していたのでしょうか?
昔の配線工事は露出配管工事が多く、壁に穴をあけ鉛詰ビスで固定したり、コンクリートやタイル、ブロックへの配線は、碍子にてバインド線で固定したものです。
電線の接続方法も今と昔では大違い、昔は電線の被覆を7センチほど剥いて、線を合わせて5~6回捻り、その上に半田付けをしてテープ巻きにする。今ではワゴや、皮つきスリーブで接続するのでテープ巻きも必要がなくなっています。
昔使用していて、今ではなくなりつつある工具や材料等、わかりますか?例えば…
- オスター(配管接続のためのネジ切り工具)
→今ではネジナシパイプにて配管、短時間で作業ができます - トーチランプ(電線の接続に使用)
→電線同士を5~6回捻り、その上に半田付けをする際に使用、今ではワゴや圧着スリーブで簡単に - ジャンピング(盤や配管を固定するためコンクリートに穴をあける工具)
→今では充電式ハンマードリルで簡単に穴があけられる
まだまだありますが、人件費が高い今日では、工数削減のため改良された多くの充電式機器類が活躍しています。昔の職人はのんびりと匠の技を披露することができました。現在は時間との戦いでそんなゆとりが無くなってきているのは、少し寂しくもあります。 (竹内寿一)
私が小学校に通い出した頃の話です。90歳近くになる祖父(創業者)が会社の倉庫の土間を、大きなU字の磁石に紐をつけて引っ張りながら歩き回っています。何をしてるのかと聞くと、その磁石を見せてくれました。「ほら、抜いて曲がった釘やビスや、金属が一杯ついているやろ」と言いながら、拾った折れ釘を金鎚2本でトントントンと、見事に真っ直ぐに直して見せてくれました。そして言いました。「折れ釘1本も大切にしなさい、また使えるから。1円を笑う者は1円に泣くというからな…それにこうして釘やビスを拾っていると車のパンクも防げるから」。小さかった私が、いまだに忘れない思い出です。
祖父の教えを守った叔父も、何でも大切に残し、分類して倉庫に置いておく人でした。私が入社してすぐの頃、ある方が「こんな金具はないか?」と尋ねてこられました。叔父が「それなら、近所のM金物さんへ行かれたらきっと有りますよ」とお伝えすると、「いや、実は今M金物さんへ行ったけれど無かった。そこの番頭さんが『そうや、山科電気へ行けば、ひょっとして似たものが有るかもしれない』というので来てみました」とのこと。叔父とその方は時間をかけて、なんとほぼ同様のものを見つけ出しました。そのお客様は喜んで帰って行かれました。叔父もまた、いつ使えるかわからないものを残しておいたが、役に立ってよかったと大喜びでした。ちなみにM金物様は「建築金具でM金物に無いものは無い」と言われる全国で高名な金物店です。
きっと昔は、消耗品といえども金属類は高価なもので、翻って今日は、このような消耗品よりも人件費が格段に高価となり、人がこのような作業をしたり、管理をしたりすることは大きな無駄と考えられ、なくなってきたように思います。でも「1円を笑う者は1円に泣く、釘1本も大切に」の精神はしっかりと受け継いでゆきたいと思います。(山科隆雄)


